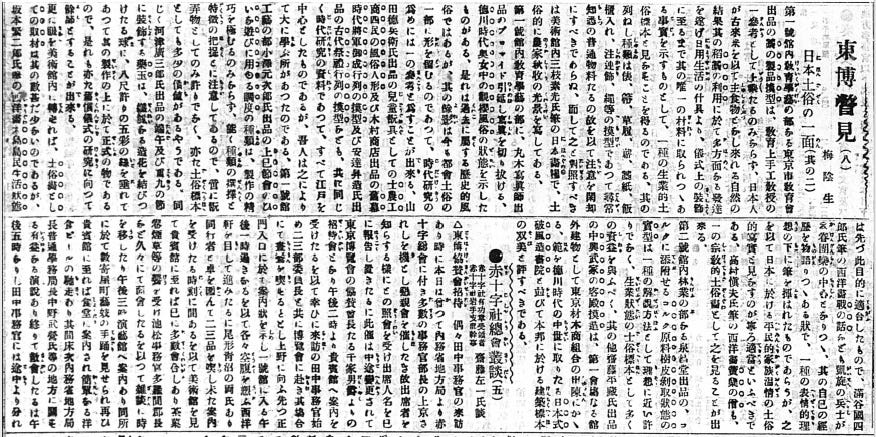アトムとビットが連続する世界ではデジタルデータにも「付喪神」が宿る
週刊メディアヌップ#20
暑いのが好きなので毎日とても気分がいいです。
今週のナイン・ストーリーズ
2022年6月22日〜2022年6月28日
1. OpenSeaがEIP-2981の対応に言及
簡単に言うと、これまでは限定的な状況でしか発生しなかった二次流通のロイヤリティの可能性が、OpenSeaのEIP-2981の対応によって広く開かれるということになります。
それに対して永井さんが指摘しているのは、「ところで二次流通のロイヤリティの徴収には何の根拠があるの?」ということです。
世の中に広く流通している言説は「転売によって生じた利益がクリエイターの元にも転がり込んでくる!」というあたらしい仕組みに興奮しているだけの話に過ぎないわけですが、では、その仕組みがセカンダリマーケットで売買する人のお財布からたとえば10%なりのロイヤリティを徴収していく根拠はなんなのかと。
たとえば私が作った「A Wizard of Tono」の場合は、Utilityのひとつとして設定した「著者コミュニティ」を継続的に運営するための資金として二次流通の何%かをロイヤリティとして設定しようかという話が制作段階で出ました。しかし結局は、著者コミュニティの継続性をわずか10%のロイヤリティによって約束することは無理だと考え、「A Wizard of Tono」には二次流通になんのロイヤリティも設定していません。このNFTホルダーは、転売した価格そのままを手にすることができますし(実際にはマーケットプレイスの手数料がとられますが)、それを購入する人にとってもロイヤリティが価格に転嫁されるということがありません。いまのところ無根拠に一般化されている二次流通のロイヤリティをあえてやっていない理由には、こうした背景があります。このあたりの話は、「メディアヌップ#032」でも語っていますので、ご興味ある方はどうぞ。
2. デジタルの付喪神
井辻朱美さんのエッセイ集『ファンタジーを読む』(青土社, 2019)のなかで非常に印象的だった一節。次の小説に織り込もうと思って引き出しの手前に入れておいたアイデアだったんですが、NFTの制作を通じて実感が強くなりました。
こんな内容です。
現代において書物は印刷から電子文字の情報へ移行し、楽器の音はコンピューターで作られ、画像は一瞬に複製され、3Dプリンターは設計図からただしに本体を生み出している。文化を支えてきたすべての道具から、それに働きかける物理的力や職人技、また固有の物質性が剥奪され、みるみるうちにサイバー世界の記号へと解体されてゆく時代である。
W・ベンヤミンが言うように、モノのオーラや唯一性も失われてゆくかのごとく見えるのだが、こうして「つくも神」というポイントから考えると、実はそうではないことが見えてくる。
物質が情報に転換される、ということは、そうした流動的な量子力学的なエネルギーと固い物質が、スペクトルの中で連続になることだ。つまりモノが情報化・エネルギー化されることにより、より生命化(アニメイト)されうるという感覚も、私たちの心の中で自然になってきたように思われる。
自然から生まれた妖精に加えて、人工のモノに魂が宿る「つくも神」が、人にとって新たな親和的「環境」を作り出す時代はすでにやってきている。
アトムとビットが連続する世界では、デジタルデータにも付喪神が宿り得る。このアイデアは、電子書籍でありながらアウラの復活をねらった「A Wizard of Tono」を励ますものであり、私が大事にしている考え方です。
3. 近代書籍の旧字や複雑なレイアウトに対応したOCRソフト発売、90%以上の読み取り精度
数年前、伊能嘉矩が遠野新聞にだけ書き残した連載原稿を翻刻するというボランティアに参加したことがあったのですが、100年ほど前の印刷媒体の文字をほぼ手作業に近いやり方でひろっていくのは本当に難しいなと実感しました。実物がこちら。
こういうものを高い精度で読みとってくれるOCRソフトには、アーキビアンとして興味津々です。
4. 罰金650億円でGoogleが学んだニュース使用料「誠意ある交渉」のやり方
最近また「Google ニュースエクイティファンド」が話題になりましたが、Googleと世界各地のメディアとの交渉のヒストリーが非常によくまとまっているおすすめ記事です。
状況は移り変わっていくので、WhatではなくWhyについて簡単に書き留めたいのですが、「大手プラットフォームへの不信が募っている」「大手プラットフォームの透明性を高めようという動きがどんどん広がっている」ゆえにこの手のニュースは大事なんですね。継続的にウォッチしたいと思います。
5. Web3革命の舞台裏(前編):痛々しいまでの理想主義と、挫折した分散化の夢
これを読んで「完全に同意」と思ってしまう自分を、「WIRED史観に毒され過ぎているんじゃないか?」と疑ってしまいました。それくらい完全に同意。一部を抜き出してコメントしてみます。
Web3を理解する方法のひとつは、まさにその名称のなかにある。つまり、Web2.0の後継者なのだ。
私もそのように説明します。もっといえば、パーソナルコンピュータという思想の後継者でもあり、ワールド・ワイド・ウェブという思想の後継者でもあると説明します。多くの人が見てきた夢が、新しい技術を背景に蘇ったのがWeb3です。
2000年代半ばになると、新たなプラットフォームとテクノロジーのおかげで一般のユーザーがコンテンツを作成してアップロードし、数千人、さらには数百万人という人々に届けることが可能になり、再び希望が見えてきた。発信者のつくるメディアを大衆が受動的に消費するのがWeb1.0なら、Web2.0では大衆がクリエイターとなる。ウィキペディアの項目、アマゾンの商品レビュー、ブログ記事、YouTube動画、クラウドファンディングのキャンペーンなどを誰もが発信できるのだ。『タイム』誌が06年に選んだ「パーソン・オブ・ザ・イヤー」は、まさにこの時代の世相をとらえていた──「あなた」としたのだ。
しかし、その水面下の状況はかなり異なっていた。ユーザーが生成するコンテンツは無償労働であり、プラットフォームこそが上司なのだ。大企業はユーザーデータを吸い上げ、そのデータと昔ながらのM&Aを利用しながら、自社のビジネスを堀で囲んで競争力を固めた。現在、ユーザー数で見た世界4大SNSアプリのうちの3つをメタ・プラットフォームズ(旧社名はフェイスブック)1社が所有している。4つめのYouTubeを所有するのは、インターネット検索で約90%のシェアを占めるグーグルだ。これらの企業がウェブの支配を広げていくにつれ、ユーザーは創造のパートナーというよりも永遠に原料を絞り出せる収穫源であることが明らかになった。
YouTubeのことを「クリエイターエコノミー」の代表例のように呼ぶ人が見かけることがありますが、その度に「全然違うんだけどな〜」と思うのはこのあたりの認識からです。ギグワーカーを量産する甘言としての「クリエイターエコノミー」という語は意識して遠ざけたい。
6. クリプトの冬、Web3の夏、そしてグリーンピル:SZ Newsletter VOL.140
編集長・松島さんのコメントから気に入った部分を抜粋。
Web3の可能性を熱く語るWeb3スタートアップの登壇者たちは、絶好調の自社のサービスがけっきょくのところWeb2的なプラットフォームとどう違うのかを、説明できずにいるように思えた。政治家たちは、DAOという思想と自分たちの職業との親和性について、深く考えないことにしているのかもしれない。
こういう視点を提供するのがメディアの仕事だよなと力強く頷きます。
この手の言説でいま特に気になっているのは、地方創生文脈で語られるDAOです。その可能性については私も大いに期待し、また自分としても具体的に活動をしているのですが、こういう場でJOIさんが紹介する事例は現時点では中身が薄い(ちなみに、山古志村のことではありません。他の例です)。もちろん、紹介される側に罪はなく、身の丈にあったやり方を地道にひとつずつ積み上げていくしかない段階にあるというだけの話なのですが、そこで紹介される事例をメディアが無批判に礼賛するとしたらそれは仕事の放棄であり罪だと思う。でもどうやらWIREDはそうではなさそう。
7. Niantic創業CEOジョン・ハンケ氏インタビュー:『メタバースは悪夢』の真意とWeb3の可能性(後編)
ハンケさんの言葉を前に取り上げたのは「週刊メディアヌップ#5」。そのときの「メタバースは悪夢」という発言に食いついて、聞き手は最終的に以下のような理解にたどり着きます。
―― 完璧に理解しました。正直なところ、昨年この『メタバースはディストピアの悪夢』が公表されたときは、反論や反発よりもむしろ困惑という反応が多くありました。ポケモンGOはいまも大人気で、ARがとても楽しく可能性に満ちているのはみな分かっているのに、なぜ唐突にリアルワールドじゃないほうのメタバースを下げる必要があったんだ?それぞれの良さがあるんじゃ駄目なの?と。
それがやっと分かりました。限定されたメタバースを誰もが使わざるを得ないよう強制したり、リッチな現実の体験から遠ざけてしまうのが悪夢という趣旨だったと。では「難しい質問タイム」はこれで終了。別に難しくもなかったですね。
聞き手自身が書いていますが、別に難しくもない話にこのような困惑を感じ、またそれなりの文字数を割いてインタビューがなされたということが、個人的には不思議でした。「なんでこんな簡単なことがわからないんだろう?」という不思議です。それは単に現時点のメタバースやXRといったものに対する関心や愛着の差によるものなのかもしれませんが、だとすればこそ、自分の関心や愛着とは明確な違いをもつ「テクノエッジ」という新媒体のことが気になってきました。今後も楽しみに読みたいと思います。
機械翻訳を頼って、最後のパラグラフを引いてみたいと思います。
24歳のミームメーカーは、@neoliberalheavenというInstagramのアカウントで、ポップカルチャーに影響を受けたコラージュと、ネット上の政治的言説のパロディーを重ねて作っている(彼は、将来の仕事の機会を制限したくないことと、匿名であることが彼の取引の一部であることから、この記事のために匿名であることを要求しました)。彼のフィードを目にする人々は、彼の作品をそれ自身のために評価することができ、彼が誰であるかは気にしないと彼は言った。また、匿名アカウントは、個人的なブランドになる可能性を排除しているため、一部の視聴者には、何かを売ったり、スターになろうとしたりしないため、より「本物」、あるいは「純粋さの新しい源」として映っているとのことです。インターネットにおける本物志向は、もはやガラス越しの世界なのです。
インターネットを愛する者として、これはすべて納得のいくことです。なぜ、誰もが常に公に生き、書き、考えなければならないのでしょうか。なぜ、そのように制限されなければならないのか。インターネットについて報道するジャーナリストとして、私ももどかしさを感じています。ここ数年、より多くの情報源が原則的に匿名を求めるようになっています。具体的な、あるいは起こりうる結果を恐れてのことではなく、名前を出されることに価値がないように思えるからです。これは、何かを本気で言おうとしないこと、そして、誰もがクールで、とてもクールで、特定することが不可能な、ある種の悲しい、少し偏執的な近未来の前兆であると考えざるを得ません。
私がおもしろいと思ったのは、匿名を希望するユーザーや取材元の気持ちについてよく理解し納得しつつも、それが「誰もが何かを本気で言おうとしない、偏執狂的な近未来の前兆かもしれない」と心配している点です。私も今では偽名(匿名ではなくあえて「偽名」と呼びます)を好み、アイコンも抽象的なものを選び、そしてまたDiscordのようなコミュニティを好んでいますが、そこで生じている気持ちは「クール」とは真逆です。熱いです。
著者の心配が自分にはよくわからなかったという点で、印象的なコラムでした。
9. UtilityのないNFTは無価値か
非常に興味深い議論が交わされていたので、目に留まった一部をまずご紹介します。
私がNFTについて説明するときは、「ただのJPEGでしょ?」と思っている人に向けて話すことが多いため、自然とUtilityについての情報が多くなるのですが、そして現に私のプロジェクトもUtilityが手厚く付いているのですが、実際には、「ただのJPEGでもいいじゃん」「ただのNFTだってありだよ」と思っています。
反対に、その価値を過度にUtilityに依存しているNFTがあるとすれば、それは本来ならNFTでなくったっていいものです。自分のプロジェクトの例でいえば、「A Wizard of Tono」は電子書籍をダウンロードできるというUtilityを売っているわけではなく、「あの本を持っている」という体験を売っているわけです。しかしそれをそのように感じてもらうためには、さまざまな世界との連続性が必要です。ここでいう「連続」とは、「アトムとビットが連続する世界ではデジタルデータにも付喪神が宿り得る」というアイデアにおける「連続」と同じで、スペクトラム状といったらいいのか、織物といったらいいのか、周辺世界に埋め込まれている必要があるわけです。
このように「NFTってただのJPEGでしょ?」という疑問から「UtilityのないNFTは無価値である」という議論を経て「ただのNFTだってありだよ」という地点に戻ってきてみると、またひとつ成熟の階段を登ったなという感覚がしてまいります。ちょうどこんなコラムも目に留まりました。
この問いに対する一つの解答が新たな「ユーティリティ」の投入であることは間違いないように思えますが、それが一時的な興奮を満たすためだけに記号として消費されるユーティリティなのであれば、その興奮が覚める前に新たなユーティリティをその度に投じ続けなければ注意を引き続けることができない、それはまるで賽の河原で石を積んでいるようなと形容できそうな行為を意味しているようにも思えます。
本当に季節が一巡りした感じがありますね。暑い冬がやってきそうです。
あとがき
9年ぶり? 気分が一周してTumblrを再開してみようかという気になっています。
https://medianup.tumblr.com/